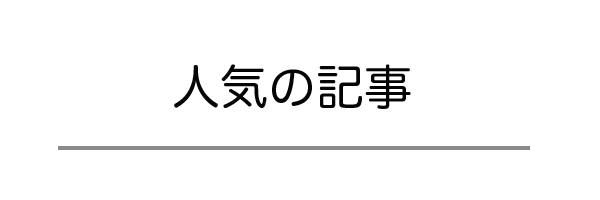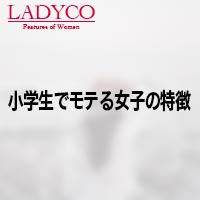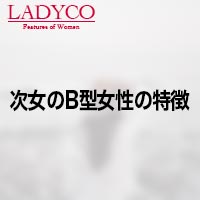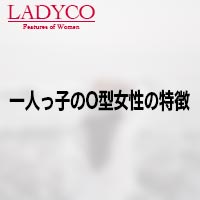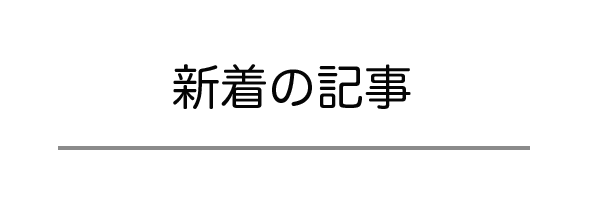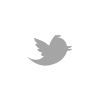同窓会は懐かしい友人と再会することができるのにもってこいの場ですよね、そんな同窓会を開くためにリーダーとなってくれるのが幹事の仕事です。
幹事は同窓会をスムーズに円滑に行うためにさまざまなことをやらなくてはなりません。
今回は同窓会をするための幹事が気をつけることについてご紹介したいと思います。
- 幹事会のメンバーをつくる
- 幹事会を行う
- 日時を決める
- 同窓会をする場所を決める
- 同窓会の予算を設定する
- 会費の金額を決める
- 同窓会の案内状作り
- 同窓会の名簿を作成
- 同窓会の進行を決める
- 当日と集計
- まとめ
1. 幹事会のメンバーをつくる

同窓会の幹事は、たいてい男女2名で行うことが良いとされます。
何故なら、幹事は男性への連絡と女性への連絡の両方を行わなくてはならないため同性同士の方が連絡しやすい場合が多いのです。
男女2名の幹事は何人かのリーダーを集めます。
2人だけで同窓会を取りまとめるのには無理があるからです。
適切な人数は、各クラス1から2名ずつくらいのリーダーを選びクラス単位で連絡事項を回してもらうようにすることが連絡が円滑に行われるポイントでしょう。
幹事会に参加してくれるリーダーは連絡がつきやすく頼みやすい人にお願いするか、勇姿を募るなどすると良いでしょう。
2. 幹事会を行う

幹事会のメンバーが選出されたら次は幹事会を行うようにします。
顔合わせのようなことをして今後同窓会が行われるまでの連絡や決定事項を決めておくことが同窓会をきちんと進める秘訣かもしれません。
メンバー同士のコミュニケーションができてなければこれからおこなわれる同窓会は円滑に運ばなくなってしまいます。
そのためには、幹事会の結束力が大事になってくるのです。
3. 日時を決める

同窓会を行うためには、日時決定をしなくてはなりません。
遠方に住んでいる人もいる場合はなるべく休みの利用できるようにしなくてはなりません。
例えば、帰省しやすいお盆やお正月、連休などがある月などに絞って決めることが重要です。
普段の日や普通の休日などは近くの人は来れるけど遠方の人は来れなくなるため出席率が悪くなる可能性があるのです。
4. 同窓会をする場所を決める

同窓会の日程がきまったら今度は、場所選びです。
人数の決定はまだですが、同窓会の規模を決めてから場所を設定します。
例えば、学年全部の同窓会だとホテルやパーティーができる会場を探さなくてはなりませんが、クラブやクラスのみの同窓会なら居酒屋やちょっとしたカフェなどを貸し切って行えば良いでしょう。
そして、気をつけるのは場所を決める時は、アクセスが良いところにすることです。
電車やバスを乗り継いでの場所は人が集まりにくくなってしまいます。
乗り継ぎがない大きな駅があるところの場所を選ぶようにしましょう。
5. 同窓会の予算を設定する

同窓会の場所がきまったら予算です。
場所を決めるときにはおおよその予算は決めているでしょう。
ホテルならネームバリューのあるところだとそれだけで予算が多くなってしまいます。
どのくらいのランクの場所でどのくらいの料理を出すかなどを決めることが大切です。
後から文句が出るのが場所と料理です。
ここはしっかり意見交換し決定するようにしましょう。
6. 会費の金額を決める

同窓会の予算が決まれば次に決めるのは会費です。
もちろん、全体の予算を決める時だいたいの一人あたりの会費は考えながら決めなくてはなりませんが、最終的に一人あたりの会費を決定していかなくてはなりません。
例えば、男性は6000円女性は5000円など男女差をつけるか、それとも男女とも同じ年齢の同級生なのだから同じ金額にする方が良いのか。
なども同窓会の幹事会のメンバーが事前に情報収集しておくことも大事なのです。
この時注意しなくてはいけないのが、同窓会を開催する際さまざまな準備費用がかかることです。
案内状や会場を予約する際の前金など大きなお金がかかってしまったり、毎回メンバーが集まる時にはお茶が飲めるカフェや喫茶店、食事をする場所など細かなお金がかかるのです。
そのため、あらかじめ幹事会のメンバーが立て替えることが多いのでそのあたりも心掛けておくことです。
7. 同窓会の案内状作り

同窓会を行う時の通知方法はたいてい案内状を出すことが多いのです。
そのため、案内状の現行作りをしなくてはなりません。
この場合幹事会のメンバー全員が集まることはありませんので、文章作りが上手い人、比較的時間に余裕のある人が引き受けることが多いのです。
その際、案内状の原稿は作るが印刷や送付は別の人に任せたり分担するようにします。
幹事会の中でも不公平感が合ってはまとまりがつかなくなってしまうからです。
8. 同窓会の名簿を作成

同窓会を行う際の案内状は同窓会名簿を作成し送ります。
事前に実家などに連絡し転居先などの確認などをしたり、遠方で住所がわからない人は誰かに聞いたりして現住所の確認をとらなくてはいけないのです。
最近では、個人情報などの規制が厳しくなかなか現住所がわからず苦戦することも多いようです。
9. 同窓会の進行を決める

同窓会の当日どのような流れにするか進行を決めるのも幹事の仕事です。
みんなが楽しめる同窓会にするためにはただの食事会で終わらせてはいけないからです。
出し物をするのかどうか、誰我挨拶するかなども周りからの情報により決めていきます。
10. 当日と集計

同窓会の当日は会費を集めたり進行役をしたり幹事は大忙しです。
そして、同窓会が終わると集計をして会場や経費の支払いなどを行います。
この時、建て替え分などの清算もして幹事の仕事が終わります。
まとめ

同窓会の幹事の仕事は大変です。
でも、懐かしい顔ぶれにあえて皆が喜んでくれるとやった甲斐がありますよね。
同窓会は懐かしい友人と再会することができるのにもってこいの場ですよね、そんな同窓会を開くためにリーダーとなってくれるのが幹事の仕事です。
幹事は同窓会をスムーズに円滑に行うためにさまざまなことをやらなくてはなりません。
今回は同窓会をするための幹事が気をつけることについてご紹介したいと思います。
1. 幹事会のメンバーをつくる

同窓会の幹事は、たいてい男女2名で行うことが良いとされます。
何故なら、幹事は男性への連絡と女性への連絡の両方を行わなくてはならないため同性同士の方が連絡しやすい場合が多いのです。
男女2名の幹事は何人かのリーダーを集めます。
2人だけで同窓会を取りまとめるのには無理があるからです。
適切な人数は、各クラス1から2名ずつくらいのリーダーを選びクラス単位で連絡事項を回してもらうようにすることが連絡が円滑に行われるポイントでしょう。
幹事会に参加してくれるリーダーは連絡がつきやすく頼みやすい人にお願いするか、勇姿を募るなどすると良いでしょう。
2. 幹事会を行う

幹事会のメンバーが選出されたら次は幹事会を行うようにします。
顔合わせのようなことをして今後同窓会が行われるまでの連絡や決定事項を決めておくことが同窓会をきちんと進める秘訣かもしれません。
メンバー同士のコミュニケーションができてなければこれからおこなわれる同窓会は円滑に運ばなくなってしまいます。
そのためには、幹事会の結束力が大事になってくるのです。
3. 日時を決める

同窓会を行うためには、日時決定をしなくてはなりません。
遠方に住んでいる人もいる場合はなるべく休みの利用できるようにしなくてはなりません。
例えば、帰省しやすいお盆やお正月、連休などがある月などに絞って決めることが重要です。
普段の日や普通の休日などは近くの人は来れるけど遠方の人は来れなくなるため出席率が悪くなる可能性があるのです。
4. 同窓会をする場所を決める

同窓会の日程がきまったら今度は、場所選びです。
人数の決定はまだですが、同窓会の規模を決めてから場所を設定します。
例えば、学年全部の同窓会だとホテルやパーティーができる会場を探さなくてはなりませんが、クラブやクラスのみの同窓会なら居酒屋やちょっとしたカフェなどを貸し切って行えば良いでしょう。
そして、気をつけるのは場所を決める時は、アクセスが良いところにすることです。
電車やバスを乗り継いでの場所は人が集まりにくくなってしまいます。
乗り継ぎがない大きな駅があるところの場所を選ぶようにしましょう。
5. 同窓会の予算を設定する

同窓会の場所がきまったら予算です。
場所を決めるときにはおおよその予算は決めているでしょう。
ホテルならネームバリューのあるところだとそれだけで予算が多くなってしまいます。
どのくらいのランクの場所でどのくらいの料理を出すかなどを決めることが大切です。
後から文句が出るのが場所と料理です。
ここはしっかり意見交換し決定するようにしましょう。
6. 会費の金額を決める

同窓会の予算が決まれば次に決めるのは会費です。
もちろん、全体の予算を決める時だいたいの一人あたりの会費は考えながら決めなくてはなりませんが、最終的に一人あたりの会費を決定していかなくてはなりません。
例えば、男性は6000円女性は5000円など男女差をつけるか、それとも男女とも同じ年齢の同級生なのだから同じ金額にする方が良いのか。
なども同窓会の幹事会のメンバーが事前に情報収集しておくことも大事なのです。
この時注意しなくてはいけないのが、同窓会を開催する際さまざまな準備費用がかかることです。
案内状や会場を予約する際の前金など大きなお金がかかってしまったり、毎回メンバーが集まる時にはお茶が飲めるカフェや喫茶店、食事をする場所など細かなお金がかかるのです。
そのため、あらかじめ幹事会のメンバーが立て替えることが多いのでそのあたりも心掛けておくことです。
7. 同窓会の案内状作り

同窓会を行う時の通知方法はたいてい案内状を出すことが多いのです。
そのため、案内状の現行作りをしなくてはなりません。
この場合幹事会のメンバー全員が集まることはありませんので、文章作りが上手い人、比較的時間に余裕のある人が引き受けることが多いのです。
その際、案内状の原稿は作るが印刷や送付は別の人に任せたり分担するようにします。
幹事会の中でも不公平感が合ってはまとまりがつかなくなってしまうからです。
8. 同窓会の名簿を作成

同窓会を行う際の案内状は同窓会名簿を作成し送ります。
事前に実家などに連絡し転居先などの確認などをしたり、遠方で住所がわからない人は誰かに聞いたりして現住所の確認をとらなくてはいけないのです。
最近では、個人情報などの規制が厳しくなかなか現住所がわからず苦戦することも多いようです。
9. 同窓会の進行を決める

同窓会の当日どのような流れにするか進行を決めるのも幹事の仕事です。
みんなが楽しめる同窓会にするためにはただの食事会で終わらせてはいけないからです。
出し物をするのかどうか、誰我挨拶するかなども周りからの情報により決めていきます。
10. 当日と集計

同窓会の当日は会費を集めたり進行役をしたり幹事は大忙しです。
そして、同窓会が終わると集計をして会場や経費の支払いなどを行います。
この時、建て替え分などの清算もして幹事の仕事が終わります。
まとめ

同窓会の幹事の仕事は大変です。
でも、懐かしい顔ぶれにあえて皆が喜んでくれるとやった甲斐がありますよね。